フランスの著名な人類学者・歴史家エマニュエル・トッドの「西洋の敗北」は、昨年フランスでベストセラーとなった注目すべき著作だ。伊藤貫氏はこの著作を「単なるウクライナ戦争の分析にとどまらず、西洋文明そのものの深い崩壊を鋭く指摘している」と評価している。この記事では、伊藤氏による解説を基に、トッドの分析の核心に迫ってみたい。
西洋文明の三段階崩壊:キリスト教的価値観の喪失
トッドによれば、西洋文明の最大の問題は宗教、特にキリスト教的価値観を失ったことにある。この崩壊は3つの段階で進行した:
- 第一段階(18世紀中頃):啓蒙主義と理性崇拝の台頭により、神を否定し人間の理性を絶対視する思想が広まる。フランス革命はまさに「神を叩き壊してキリスト教文明を叩き壊し、理性を崇拝する」革命だった。
- 第二段階(19世紀後半):庶民レベルでキリスト教の教義に疑問を持つ人々が増加した。しかし、キリスト教の教義そのものを信じなくなっても、その価値観や人生観は3世代ほど残った。
- 第三段階(1960年代以降):カウンターカルチャー、フリーセックス、高い離婚率など、キリスト教的価値観の完全な崩壊が始まる。「自分の満足するように生きればいい」という価値観が広まり、キリスト教の影響が完全に消失した。
この結果、現代の西洋社会は「絶対的虚無状態」に陥っている。人々は神や超越的な価値規範を失い、三つのP、すなわちパワー(権力)、プロフィット(利益)、プレジャー(快楽)の最大化だけを追求する浅薄な存在になった。
かつて人間は、自らの価値判断を超えた神聖な価値規範を求めて生きていた。ソクラテス、プラトン、キリスト教神学に至るまで、2500年前から1750年頃まで続いたこの思想が、わずか200年余りで崩壊してしまったのである。
伊藤氏は、「人間の欲望や利害打算を超越した物の見方をしないと、人間は質の高い生き方ができない」と指摘する。しかし、トッドはより悲観的で、一度失われた神への信仰は二度と戻らず、西洋文明はさらに悪化するだけだと考えている。
人類学と国際政治:家族構造が生み出す価値観の対立
トッドの分析の独自性は、人類学と国際政治学を融合させた点にある。彼によれば、家族関係のパターンが人間の思考様式や価値判断を形成し、それが国家間の政治関係にも影響を与えている。
世界の家族構造は大きく分けて:
- 個人主義的核家族(英・米・仏):個人の自由と利益を最大化する価値観
- 父系制の権威主義的家族(日本・ドイツ):長男が父親の財産を継承する家族システム
- 平等主義的大家族(ロシア・中国):兄弟平等に扱う大家族システム
興味深いことに、西洋的な個人主義的価値観は人類の10〜15%程度しか持っておらず、世界の圧倒的多数は大家族的価値観を持つ社会に属している。このことは国際政治を理解する上で極めて重要だ。
トッドは、「アメリカ政府は世界の諸国が人類学的な多様性を持っていることを否定し、自らの均一的な国際政治観を絶対視して他の国に介入してくる」と批判する。例えば、アメリカは急進的なフェミニズムやLGBTQの価値観を世界中に押し付けようとするが、世界の大多数の家族システムにとって、これらは受け入れがたい価値観なのだ。
実際、ロシアのウクライナ侵攻に対する経済制裁に参加したのは世界人口の約12%に過ぎない。トッドによれば、ロシア政府が主張する「グローバル・マジョリティ(世界の多数派)」という概念は人類学的に見れば正しいのである。
高等教育の拡大がもたらした逆説的な知性の低下
トッドの分析で特に興味深いのは、高等教育の拡大がむしろ社会の知性を低下させたという逆説だ。彼はこれを「高等教育による知性や道徳規範の劣化現象」と呼んでいる。
彼のリサーチによれば、アメリカで高等教育を受けた人口が25%に達した1965年以降、あらゆるレベルで知的衰退が始まった。大学入学試験(SAT)の成績も、国民全体のIQも低下しているのだ。
高等教育を受けた層は「大衆化したエリート」となり、真の教養や深い思考力を持たないにもかかわらず、自己優越感に満ちている。彼らは:
- 自分よりも教育レベルの低い層を軽蔑し見下す
- 社会の不平等を正当化する(「彼らは劣等だから貧しいのは当然」)
- 社会の分断を深め、協力関係を破壊する
伊藤氏は、自身の経験からこの分析に共感を示す。「高等教育を受ければ人間が上等な連中になるかというとそうではなく、むしろ優越感の塊で周りの国民を軽蔑する人間になる」と述べている。
ワシントンDCの郊外など学歴レベルが世界で最も高い地域の住民でさえ、真の思考力や教養を持っているわけではない。伊藤氏は「高学歴だから深い思考力があるとか、まともな価値判断力があるかというと全然別の話」だと指摘する。
皮肉なことに、150年前のエリートと比べると、現代のエリートは専門知識は増えているものの、全般的な教養、文化、思考力においては遥かに劣っているのだ。
アメリカの没落と日本への影響
トッドは、ウクライナ戦争でのアメリカとNATOの失敗は西洋の敗北を象徴するものであり、これによってNATOは崩壊する可能性が高いと予測している。
彼によれば、アメリカの外交政策の最重要事項は「ドイツと日本をアメリカの永遠の属国にしておくこと」だ。これはズビグネフ・ブレジンスキーの著作で明確に述べられている。アメリカが両国に大量の米軍を駐留させ続けるのは、「外敵から守るため」ではなく、「両国が軍事的・外交的に独立できないように監視し続けるため」なのだ。
さらに、アメリカの外交政策は、アメリカ国内での不平等と同様に、同盟国内部の経済格差も拡大させる効果がある。伊藤氏によれば、「最近35年間アメリカ政府が日本に突きつけてきたほとんどの経済的な要求は、日本国民同士の経済格差を広げるものだった」。
しかし、西洋文明の崩壊に伴いアメリカの道徳的基盤も失われ、「裏切りが普通になっている」状態だ。トッドは断言する:
「アメリカは中国に対抗して日本と台湾を守らないだろうと確信している」
日本への示唆:自主防衛の必要性
トッドの分析から日本が学ぶべきことは明確だ:
- 自主防衛の確立:アメリカへの過度の依存は危険であり、自主防衛能力(場合によっては核抑止力)を持つべき。トッドは「日本は中国から自国を守るために自主的な核抑止力を持って自主防衛しなければならなくなるだろう」と述べている。
- アメリカへの過信を避ける:「アメリカは同盟国としての信頼性が低い国だから」と警告し、「いつ裏切られるかわからないから、アメリカとの同盟関係に関しては慎重になった方がいい」とアドバイスしている。
- 多極的世界観の採用:「ロシアは多極的な世界というものを作ろうとしている。しかし西側諸国は西洋中心の均一的な世界というビジョンを押し付けようとしている。日本的な観点からするとロシアの多極世界を目指すロシアの考え方の方が日本の気質に適合しているのではないか」という視点も提示している。
結論:西洋の没落と世界秩序の再構築
エマニュエル・トッドの「西洋の敗北」は、単なる国際情勢分析を超え、西洋文明そのものの根本的な問題を浮き彫りにしている。キリスト教的価値観の喪失、高等教育の拡大がもたらした逆説的な知性の低下、そして世界の多様な家族構造と価値観を無視した西洋の一元的世界観の押し付け—これらすべてが西洋の衰退を招いているのだ。
トッドは悲観的な見方をしているが、伊藤氏はより建設的な立場を取る。「宗教をもう一度復活させなくても哲学的な見地から神の存在を信じることは十分可能」であり、「人間の世俗的な利害打算を超越する思考パターンを持っていないと人間はどんどん矮小になっていく」と指摘している。
日本を含む非西洋諸国はこの歴史的転換点で、西洋に単に追従するのではなく、独自の立場から世界秩序の再構築に関わっていく必要がある。そのためには、アメリカへの過度の依存を避け、自主防衛能力を高め、多極的な世界観を模索する姿勢が求められるだろう。
今後のウクライナ戦争の行方について、伊藤氏は「プーチンとトランプにはある程度の信頼関係がある」ため、「今年の夏か秋頃には停戦可能な状態に行くかもしれない」と予測している。しかし、「だからといってヨーロッパなりアメリカが良い方向に進んでいくとは思えない」とも付け加えている。西洋文明自体が崩壊状態に向かっているからだ。
エマニュエル・トッドの鋭い分析は、我々に西洋文明の限界と新たな世界秩序の可能性を示している。この歴史的転換期に、日本はどのような道を選ぶべきなのか—それが問われているのだ。
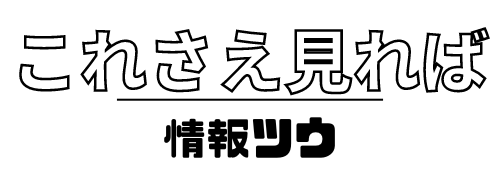
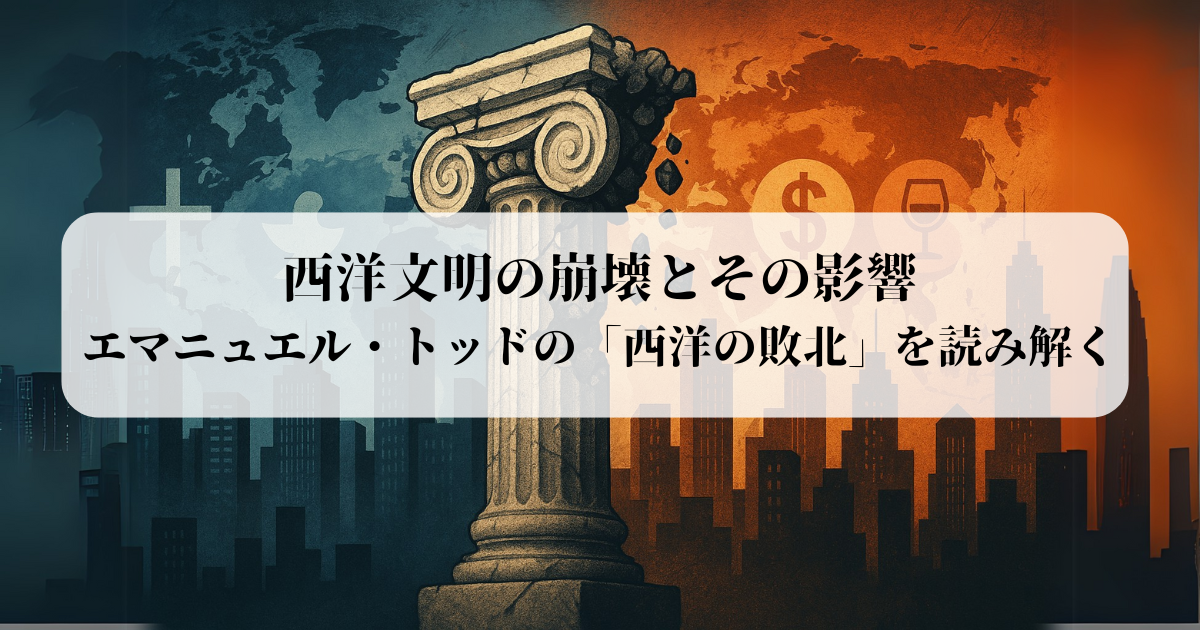
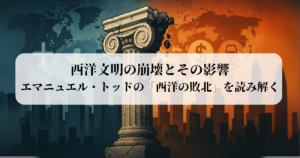
コメント