11年ぶりの来日が持つ意味
国際政治学者ジョン・ミアシャイマー教授の日本来日がついに実現することになった。前回の来日は11年前、東京財団での限定的な講演のみだった。なぜこれほど長い間、世界的に影響力を持つ国際政治学者が日本と距離を置いていたのか。その背景には、日本の外交政策エスタブリッシュメントとミアシャイマー教授の立場の根本的な相違がある。
伊藤貫氏によれば、ミアシャイマー教授は「アメリカの保守派国際政治学者の中で実力ナンバーワン」と評価される人物だ。しかし日本では、彼の理論や提言が正しく理解されていない。むしろ「いつもアメリカ政府の政策に反対している」アウトサイダーとして誤解されてきた。
オフェンシブ・リアリズムとは何か
ミアシャイマー教授の立場は「オフェンシブ・リアリズム(攻撃的現実主義)」と呼ばれる。これは国際政治を理解する上で重要な理論的枠組みだ。
保守派の国際政治学には大きく3つの流派がある:
- ディフェンシブ・リアリズム(防御的現実主義)
- オフェンシブ・リアリズム(攻撃的現実主義)
- ヘゲモニック・スタビリティ理論(覇権安定論)
リアリズム外交の基本は、政治イデオロギーや道徳観を過度に持ち込まず、大国間の「バランス・オブ・パワー(勢力均衡)」を維持することが最も望ましいとする考え方だ。ミアシャイマー教授は、大国は常に自らの軍事力と経済力を強化し、勢力圏を拡大しようとする衝動を持つと分析する。これは過去500~600年の歴史が証明している普遍的な傾向だという。
アメリカの過剰介入への一貫した批判
ミアシャイマー教授は、クリントン政権から現在に至るまで、民主党・共和党を問わず、アメリカの外交・軍事政策が「オーバーコミットメント」であり「オーバーインターベンション」だと批判し続けてきた。つまり、コミットしている地域が広すぎ、軍事介入の頻度が多すぎるという指摘だ。
具体的な批判の歴史:
- クリントン政権:セルビアへの制裁と空爆、NATO拡大政策を批判
- ブッシュ(息子)政権:イラク戦争に最初から大反対
- 2008年:ジョージアとウクライナのNATO加盟方針に反対
- 2014年:オバマ政権下でのウクライナ政変を批判、「このままでは戦争になる」と警告
これらの批判は、単なる反対のための反対ではない。すべて「バランス・オブ・パワー」の観点から、アメリカの長期的な国益を損なう政策だという理論的根拠に基づいている。
日本の外交政策の根本的問題
伊藤氏は、日本の外交政策の最大の問題は「バランス・オブ・パワー」という概念が理解されていないことだと指摘する。日本の保守派も革新派も、それぞれ固定観念にとらわれている。
左派の固定観念:「憲法9条を守っていれば大丈夫」
保守派の固定観念:「アメリカについていれば大丈夫」「日米同盟をより一層強化せよ」
日本の外務省、防衛省、自衛隊、そして保守派と呼ばれる国際政治学者たちは、「今後のバランス・オブ・パワーがどう変化し、日本としてその変動をどのように有利な方向に持っていけるか」という戦略的思考が欠けている。彼らは単に「日米同盟の深化」を繰り返すだけで、10年後、20年後を見据えた長期戦略を持っていない。
中国の長期戦略と日本の近視眼的思考
興味深いことに、ミアシャイマー教授は「中国に行くとものすごく歓迎される」と語っているという。なぜか。中国人の国際政治理解はリアリスト的であり、「ロングゲーム」を演じる才能があるからだ。中国は5年後、10年後、20年後を見据えた戦略を立てている。
対照的に日本人は「目先のことしか考えていない」。せいぜい半年、多くの人は1~2か月先のことしか考えていない。例えば現在の日中対立についても、日本のメディアは「落としどころを探る」といった短期的な妥協点ばかりを議論している。しかし中国は5年後、10年後に日本をどう追い詰めるかという長期戦略でゲームをプレイしている。
この差は歴史的背景にも起因する。中国は春秋戦国時代から、複数の国家間でバランス・オブ・パワーを演じてきた経験がある。だからこそ、ミアシャイマー的なリアリスト国際政治の考え方が「身近に聞こえる」のだ。
2035年:アジアのパワーバランス転換点
伊藤氏は衝撃的な予測を提示する。「10年後か20年後にアメリカは東アジア地域から撤退せざるを得ないだろう」。具体的には、2045年には「アメリカが東アジアを支配しているとは思えない」。早ければ2035年頃にアジアにおけるパワーバランスは中国に有利に傾き、アメリカは戦争をせずに東アジアから撤退する可能性があるという。
この予測の根拠は何か。台湾有事を例に考えてみよう。もし日本が台湾有事に介入した場合、中国は数千発のミサイルとドローンで日本を攻撃できる。日本のミサイル防衛システムは2~3日で使い果たされ、その後は「丸裸」になる。さらに中国は数百発の核ミサイルを保有しており、核による恫喝(ニュークリア・ブラックメール)も可能だ。
重要なのは、「アメリカは日本を守るために核戦争をしない」という現実だ。バイデン政権時代、プーチンが戦術核使用を示唆した際、アメリカは即座に後退した。中国が日本に対して核恫喝を行った場合も、アメリカは同様の対応を取る可能性が高い。
日本の核武装論:タブーから現実的議論へ
このような状況下で、アメリカの専門家の間から「日本に核を持たせた方が東アジアは安定する」という議論が出始めている。伊藤氏が言及した例では、カウンシル・オン・フォーリン・リレーションズ(CFR)のウェブサイトに、オクラホマ大学の軍事専門家2人が「日本に核を持たせろ」という論文を掲載した。
さらに、以下の専門家も同様の見解を示している:
- MITのバリー・ポーゼン
- テキサスA&M大学のクリストファー・レイン
- そして、ミアシャイマー教授自身
伊藤氏は、トランプ政権の主要人物であるトランプ大統領、バンス副大統領、ルビオ国務長官、そして国防次官補のエルブリッジ・コルビーの4人は、「日本がアプローチすれば日本に核を持たせるという話に乗ってくる可能性が高い」と分析する。
特にコルビーは注目に値する。彼の祖父は元CIA長官であり、陸軍の軍事学者でもあった。父親は東京に駐在し、コルビー自身も日本で数年間過ごした経験がある。彼は「本物の軍事専門家」であり、アメリカのグランドストラテジー(大戦略)を決定する立場にある。
日本の核保有反対論の幼稚さ
日本で核保有に反対する人々は、以下のような「小学生レベル」の議論をしているという:
- NPT(核拡散防止条約)違反になる
- アメリカからウラニウム・プルトニウムの輸入を止められる
- 世界から孤立する
しかし伊藤氏は、これらは「ちまちました細かい反論」に過ぎないと批判する。もしアメリカ政府のトップが「日本に核を持たせた方が東アジアは安定する」と判断すれば、これらの「問題」はすべて解決可能だ。重要なのは、過去500年間の国際政治がバランス・オブ・パワーで動いてきたという大局観を持つことだ。
1972年の米中合意という呪縛
興味深い歴史的事実がある。1972年、ニクソンとキッシンジャーが北京を訪問し、毛沢東・周恩来と会談した際、「日米同盟を維持し、日本に独立した外交・軍事政策を実行する能力を与えない」ことで米中が合意したという。
それ以前、中国は日米同盟を「中国に対抗するもの」と見なしていた。しかし1972年以降、中国は「日本を日米同盟に縛り付けておいた方がよい」という立場に転換した。つまり、米中双方にとって、日本が真の独立国になることは都合が悪いのだ。
現在の日中対立も、この文脈で理解する必要がある。中国は複雑なゲームを演じている。台湾有事に日本が介入することは阻止したいが、同時に日本が自主的な核抑止力を持つことも望まない。だからこそ、CFRが「日本の核武装」論文を掲載したことは、中国への警告の意味もあるのだろう。
自衛隊内部の本音
表には出てこないが、自衛隊内部には「台湾有事への介入はまずい」と考える人々がいるという。なぜなら、中国との軍事衝突が起これば、自衛隊は壊滅的な打撃を受ける可能性が高いからだ。中国の圧倒的なミサイル・ドローン攻撃能力と核恫喝の前では、自衛隊の防衛能力は限定的だ。
防衛研究所にはかつて平松茂雄氏のような専門家がいた。彼は15年以上前から「日中間で軍事衝突が起きたら中国は日本を核恫喝する可能性が大きく、アメリカの核の傘は機能しない。だから日本は核を持たなければならない」と主張していた。しかし現在の防衛研究所には、そのような発言をする人物はゼロだという。
結論:日本に必要なのは「リアリスト的思考」
ミアシャイマー教授の来日は、日本にとって重要な学習機会となる。日本人が最も欠けているのは「バランス・オブ・パワー」という考え方だ。アメリカにしがみついていれば安全だという「親米保守」の単純な理屈では、次の10年を乗り切れない。
2026年から2035年は、東アジアのパワーバランスが日本にとって不利な方向に大きく転換する時期になる可能性が高い。その時に備えて、日本は独立した安全保障能力を持つ必要がある。ミアシャイマー教授は35年前から「日本は実質的にアメリカに占領されている疑似独立国に過ぎない」と指摘してきた。その状況は今も変わっていない。
日本の政治家、特に自民党保守派は「勉強しない」「決まりきったことしか言えない」と伊藤氏は厳しく批判する。希望があるとすれば、「圧力をかけられても黙らない」参政党のような新しい政治勢力だという。
今こそ日本は、感情論や固定観念を捨て、冷徹なリアリズムに基づいた安全保障議論を始めるべきだ。ミアシャイマー教授の理論は、そのための重要な知的基盤となるだろう。日本の未来は、この「不都合な真実」とどう向き合うかにかかっている。
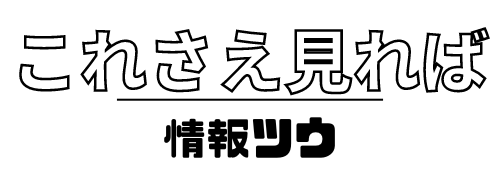
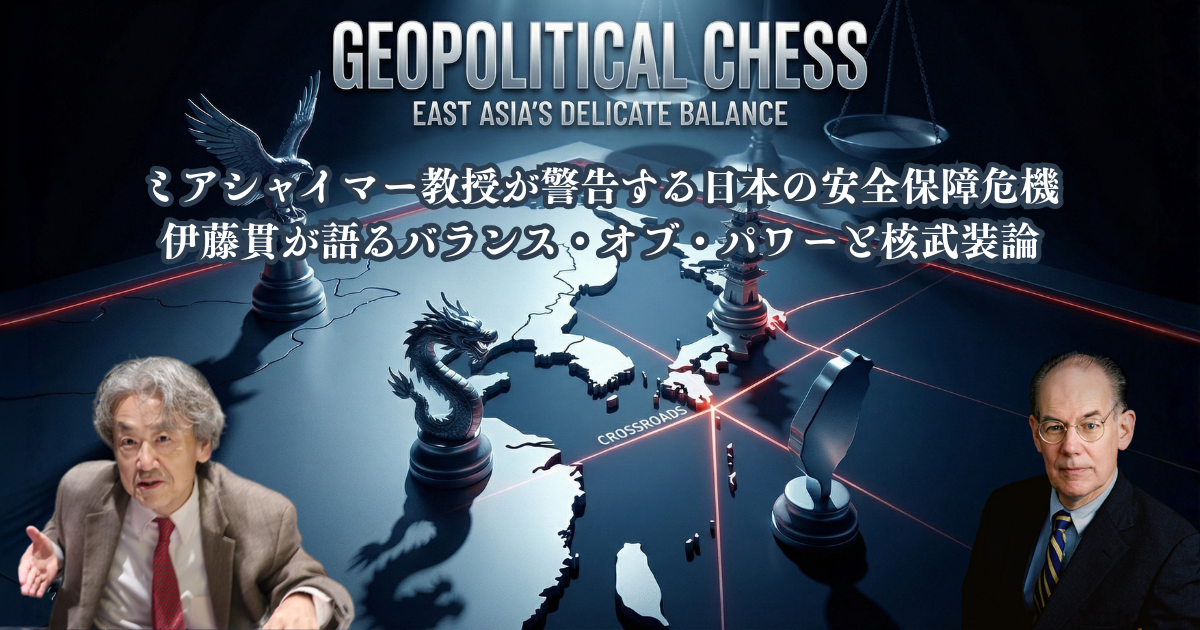
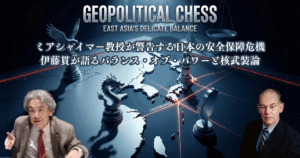
コメント